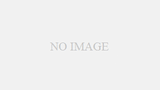10年以上保育に携わっていますが、子ども達の様子がかなり変わってきているように感じます。
「発達障害」と診断される子どもも増えてきています。
一体なぜでしょう? 果たして先天的な脳の障害がこれほど増えるものなのでしょうか?
一方で「日本は同調圧力が強いから変わっている子が目立つだけ」なんていう意見もあります。
果たして本当に?
自分なりに調べた中で、興味深かった書籍がいくつかあったので紹介させてください。
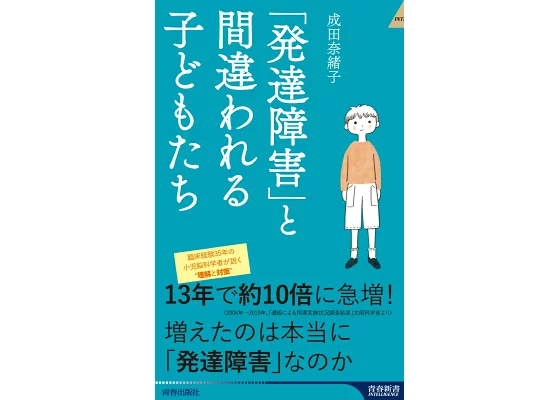
成田奈緒子著:「発達障害」と間違われる子どもたち
普段あまり本を読まない私でもすぐに読めるくらい読みやすくておすすめ!
私が園の保護者会でも紹介している1冊です。
著者によると、生活習慣の乱れによって「発達障害もどき」が増えているのだとか。
園でも連絡帳で家庭での子ども達の睡眠時間や食事の様子が確認できますが、就寝時間が23時の子どももいて非常に驚いています。
しかもほとんどの家庭が22時就寝。
「21時までに寝ましょう」と小学校でも言われていますが・。
現代の子ども達は睡眠時間が足りないのは明らかですね。
また、ゲームやスマホの影響も大きいです。
そうした不健康な生活が子どもに与える影響について書かれているのでぜひ読んでみて欲しいです!
生活習慣の乱れによる「発達障害もどき」について紹介しましたが、近年子ども達を見ていて増えていると感じるものに「愛着障害」があります。
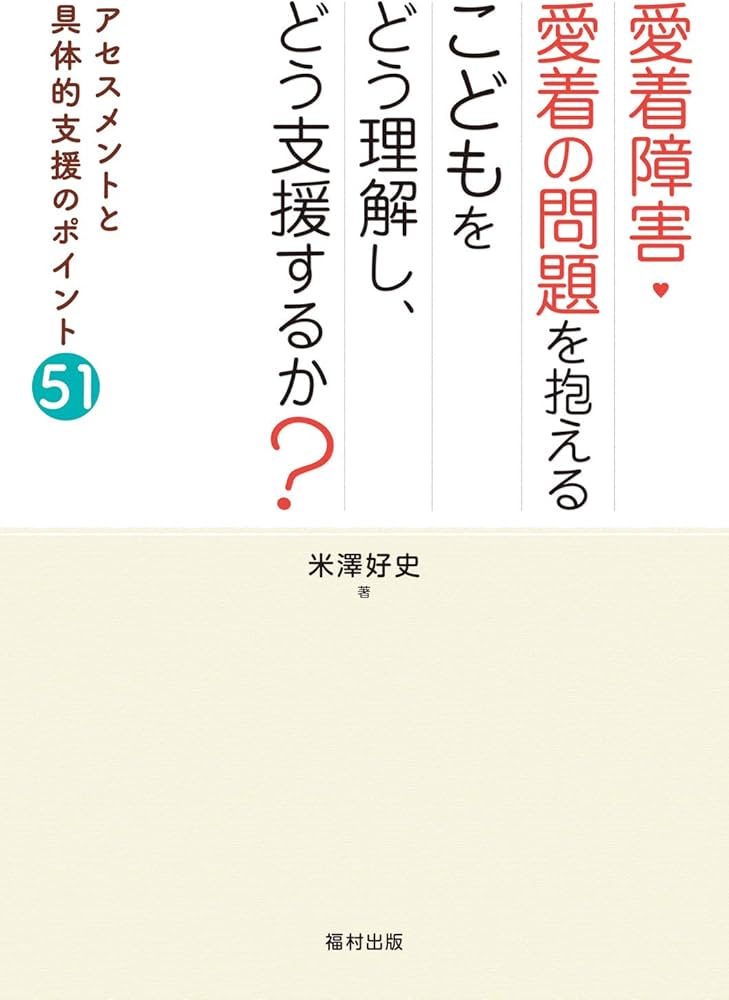

米澤好史著:「愛着障害・愛着の問題を抱えるこどもをどう理解し、どう支援するか?」
「愛着アセスメントツール」
愛着障害というと、愛情を与えていないとか虐待をしている家庭で起きる事じゃないかと思いがちで、私も実際そう思っていました。
本を読んでわかったのは、決して愛情を与えていないからではなく「親と子の愛情の行き違い」によって起こるものであり、どの家庭でも起こる可能性があるということ。
愛情の行き違いとして具体的な例をあげると…
・親は子どもを色んな所に連れていっていろんな経験をさせてあげようとするが、子どもの方は出かけるよりも家で保護者とのスキンシップを求めている。
・将来のために色んな習い事をさせてあげようとするが、子どもはあまりやりたくない。
・腫れ物扱い。(子どもが癇癪を起こさないよう親が言いなりになる)
などでしょうか。
最後の腫れ物扱いについてはこの本を読んで知ったのですが、非常に驚きました。
怒りすぎてもだめ、怒らなさすぎてもだめ、じゃあどうしたらいいんだと親御さんは途方に暮れてしまいますよね( ; ; )
しかしこの事を知って感じたのは、子どもは生まれながらにして「真人間」になるようプログラムされているんだということ。
愛情をもらう事はもちろん、人間社会で生活する上で良い事や悪い事をきちんと学ばなければ、いわゆる「発達障害」と言われるような行動が出てきてしまう。
子育てって難しいけれどとても興味深いですね!
「うちの子発達障害かしら?」と悩んでいる方は、まず生活習慣、子どもとの愛着形成ができているかを見直してみてほしいです!